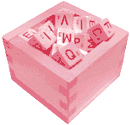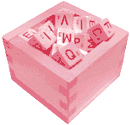“Riddle me, riddle me, what it is.”
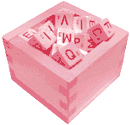
たとえばそれは、ふとしたときに見せる表情だったり、傍にいるときに纏っている雰囲気だったり、そんな些細なことだった。積み重なれば致命的な負の感情に変化し得る小さなきっかけは、ここのところずっと、ことあるごとにハン・ソロの眉間に皺を刻む原因になっていた。
たとえばそう、今まさに視線の先で、見るからに居心地の良さそうな空気に包まれて肩を叩き合う二人の友人の会話風景や、滅多に笑顔を見せないことで有名な金髪のジェダイ騎士が声をあげて笑っている姿が、苛立ちとも憤りとも呼べないもやもやとした何かを体内にわだかまらせている。
阿呆か俺は、と自嘲気味に笑い飛ばせば、やるせない苦々しさだけが胸中に渦巻いた。
新共和国の新しい首都となったコルサントの夜は、目を見張る勢いで数を増やしつづけるネオンサインと、途切れることのないエアカーのライトの洪水に彩られ、いつにない盛況振りを見せていた。帝国が倒れ、課税や規制が解かれたおかげで、銀河の中心的な都市惑星は様々な文化のるつぼとなって、かつての明るさを取り戻しつつあった。
そんな中、あまり小奇麗とはいえない繁華街の片隅にある酒場と食堂を兼ねた店が、反乱軍時代から宇宙の平和に貢献してきた高官たちの間で、密かな評判を呼んでいる。見つけてきたのが誰だったのかは定かではないが、新生ローグ中隊の指揮官であるウェッジ・アンティリーズも、その店の常連客の一人だった。
眉間に皺が寄りそうになるのを抑え、可能な限り友好的な笑顔を張りつけて、ハンは見知った顔が居並ぶテーブルに近付いた。いつものオレンジ色のフライトスーツ姿ではなく、茶系のズボンと黒いブーツに、濃い青のジャケットを羽織ったウェッジが目ざとく男の姿を見つけて、黒一色を纏う外交官の向かい側から手を振った。
「ソロ、ずいぶん遅かったな」
適当に注文しておいたからな、と気さくに声をかけてきたウェッジの横で、ルーク・スカイウォーカーは今初めて年上のスペーサーに気づいたように顔を上げ、憎たらしくなるほど礼儀正しい笑みを浮かべて、やあ、と短く挨拶した。俺が店に入って来る前から気づいていたくせに、何を言いやがる ── 喉元まで出かかった言葉を飲み込んで、男は手に持ったままだったグライダーの鍵を黒いベストのポケットに突っ込んだ。
テーブルは一つ一つがボックス席になっていて、隣客に会話内容が聞こえ難くなっているのも、人気の理由らしかった。黒髪のパイロットの隣の席につき、ハンは笑みを崩さずに向かいに座る年下の青年に喋りかけた。
「久しぶりだな、キッド」
「そうだね、最近じゃ本部ですれ違うこともないし」
限りなく友好的なその言葉は、しかし決定的に親密感を欠いていた。薄くて透明な壁が、自分と青年の間を隔てているような感覚に、歯噛みしたい気分になる。
二人の間に流れる空気がどこか余所余所しいことに気づいているのかいないのか、空いているグラスに酒を注いだウェッジは、手で摘める前菜が乗った皿と一緒にそれを差し出して寄越した。さして期待せずに流し込んだ酒は、そこそこ質の良いウィスキーで、快く喉を焼くアルコールが少しばかり男の気分を慰めた。
「ソロ、ここの料理長のことは知ってるな?」
アルコールの所為か、早い時間に仕事を抜け出せたのが嬉しいのか、機嫌の良さそうなローグ中隊長の質問に、ハンは頷いた。
「ああ、直接会ったことはないが」
隠れた名店の経営者は恰幅の良いベサリスクで、昔は腕を鳴らした密輸業者だったらしいというまことしやかな噂が流れている。同業者の勘というやつで、かつて自分も裏社会の一員として名を馳せていた男は、その風聞を八割方事実だろうと判断していた。
「なんだ、話したことはないのか?中々面白い人物だぞ。ルークを紹介しようと思って、さっき声をかけたんだ」
何かをたくらんでいるような顔でウェッジが言った。すると、エプロン姿の大柄なエイリアンが、のっそりとボックス席に近付いた。
湯気の立つ大皿が三つ、テーブルの中心に置かれ、取り皿とナイフやフォークまでが四本の逞しい腕によって次々と並べられた。
「こりゃあ珍しい集団だな、コルサントの有名人が3人も雁首揃えてお食事とは」
下方の腕を腰にあてて、低くしゃがれた声で言い放った店の主人は、染みのついたエプロンのポケットから煙草とライターを取り出し、太い指に挟まれてやけに小さく見える嗜好品に火をつけて口に運ぶと、美味そうに煙を吐き出した。
「デックス、俺たちを言い訳に休憩か?」
「調理場で吸うとフロウが五月蝿ぇんだよ」
フロウというのは給仕ドロイドの名前らしい。店内を忙しなくくるくると動き回るウェイトレスの一人が、言い訳がましい台詞に反応し、どこからか甲高い機械的な声を張り上げた。ほらな、と肩を竦めて、デックスと呼ばれたエイリアンは空いた左手で頭を掻いた。
「まるで世話女房だな」
愉快そうに笑いながら、黒髪の司令官は、エプロン姿の料理長をデクスター・ジェットスターだ、と簡潔に紹介した。初めまして、と律儀に返事をするルークとは対照的に、ハンはただ軽く頷いて見せた。
この顔合わせは、どうやら自分には余り関係がないらしいと判断した男は、さっさと出された料理を取り分け始めた。素っ気無い態度の友人をちらりと横目で見やり、ウェッジはデクスターに喋りかけた。
「仕事中に悪いな、我らがジェダイ騎士と将官殿に是非ともあんたを紹介したかったんだ」
「そりゃあいいが、冷めないうちに食ってくれよ」
料理人らしい台詞と共に口の端から煙を吐き出して、四本腕の料理長はルークに向かって聞き捨てならない言葉を放った。
「新共和国のジェダイの評判は色々聞いてる。お前さんの師匠は誰だったんだ?」
「フォースのことを教えてくれたのは、ベン…いえ、ケノービという名前の人、でした」
一瞬、微かに切なげな表情をした青年の返事を聞き、目を細めた店主は下方の右手に持ちかえた煙草から灰が落ちそうになっているのに気づき、テーブルの隅に寄せてあった未使用の灰皿を下部の左腕を伸ばして引き寄せ、紫煙をくゆらせるそれをとんとんと叩いた。
「そりゃあまた…懐かしい名前だな。オビ=ワン・ケノービか」
「ベンを知ってるんですか?」
意外なところで浮かび上がった今は亡き師の名に興奮したのか、デクスターの声を遮る勢いで反応したルークが、最近では滅多に見られないような活き活きとした表情で、身を乗り出さんばかりに早口でたたみかけた。コレリアの家庭料理に似た野菜炒めのような副菜を口に運んでいたハンは、思わず手を止めて、ため息を噛み殺した。
『ジェダイ』や『フォース』といった単語は、ルークが年上の操縦士相手に使わなくなって久しい言葉だった。自業自得といってしまえばそれまでだが、忌々しいことに変わりは無い。
まだかろうじて親しい友人というポジションを与えられているファルコン号の船長に回ってこなかった相談事は、当然のごとく他の誰かに流れていく。新共和国のジェダイ騎士殿は、いつかどこかの惑星を買い取ってジェダイ・アカデミーを開きたいらしい── 数日前に会ったベスピンの都市管理職に復帰した旧友に、青年から不動産関係の相談を受けたと聞かされ、胸倉を掴む勢いでなんでお前が、と問い詰めたことを男は苦々しい気分で思い出した。
その程度では同じないランド・カルリシアンに、『知らなかったのか?』などと嘲るように言われたことまでが脳裏によみがえり、ハンは舌打ちしたい気分になった。
「オビ=ワンとは、アウター・リムの向こう側で酒場をやってたときに会ってな。友人だったよ、随分と長いこと会ってなかったが」
「ベンは…数年前に、亡くなりました。尊敬できる師匠でしたよ」
懐かしそうに交わされる会話を聞き流し、運命を操る神秘的なエネルギーなど毛の先ほども信じていない不幸な男は、空中で停止したままだったフォークを口に突っ込んだ。どうしようもない気分を抱えて酒を呷り、急に味気なくなった料理を流し込む。
脛にいくつも傷のありそうなこの料理長は、かつてジェダイの総本山がコルサントにあった時代を知っているらしい。どこか懐かしそうに言葉を紡ぐデクスターとは対照的に、興奮気味のルークは矢継ぎ早に質問をぶつけている。
「退屈そうな顔をするなよ」
本格的に話し込んでいる二人を満足そうに見つめていたウェッジが、憮然とした表情を隠しきれていない男にしか聞こえないように、笑みを含んだ声をかけてきた。
「ジェダイ絡みの話になった途端にそれじゃ、ルークも大変だな」
何もかもをわかっているような口振りで呟かれたその台詞を、ハンが問いただそうとしたとき、随分と古びたWA-7型ドロイドが車輪を転がしてデクスターに近づいてきた。結果的に長い休憩を取ることになった料理長に詰め寄ったウェイトレスは、C-3POよりも更に早口の金切り声で、仕事に戻れと責めたてた。
「ああ、わかったわかった」
名残惜しげに最後の一服を終えた店主は短くなった煙草を灰皿に押しつけて消し、今度は暇な時に来るといい、とルークの肩を叩いて去っていった。興奮冷めやらず、といった表情を隠そうともせず、新共和国の外交官は黒髪の飛行部隊長に向き直ると微笑んだ。
「ウェッジ、ありがとう。デックスがジェダイについて詳しいって知ってたから、わざわざ紹介してくれたんだろう?」
「ああ。しかし、まさかあそこまで情報通だとはな」
和やかな雰囲気の中、ハンは少々冷めてしまった料理をつついた。いつになく饒舌な青年のテンションに反比例するように、どう頑張っても浮上できそうにない自分に気づく。聞き手に専念するしか選択肢はなく、沈んでいく気分を顔には出さないよう精一杯努力した男は、食事が終わる頃には精神的に疲弊しきっていた。
ハイペースで空けた酒も料理も、充分満足に値するものだったにも関わらず、コレリア出身の操縦士は拭いきれない敗北感を味わいながら上機嫌の友人たちに続いて席を立った。
「ソロ、土産だ」
店を出ると、意味ありげな笑みをうかべたウェッジがどこに隠し持っていたのか、酒瓶を差し出してきた。味は悪くなかっただろう?と聞いてきたところを見ると、ボトルの中身は店内でたらふく飲んだウィスキーらしかった。ラベルには、聞いたことがあるような惑星の名が印刷されている。口あたりの良いその酒は飲みやすく、普段あまりアルコールを嗜まない金髪のジェダイ騎士も、珍しく杯を重ねていた。
「ルークはお前が送って行けよ」
じゃあな、と軽く手を上げ見覚えのあるエアカーの方向へと歩いていく黒髪のパイロットの背中を見送った男は、嫌な相手に借りを作ったことに気づいた。釈然としないながらも、与えられたチャンスを無駄にするのは惜しく、ハンは傍らに佇む青年に向き直った。
「運転してきてないのか、キッド?」
「どうせ、ハンとウェッジが一緒なら、飲むと思ったから」
去って行った友人の言葉を計りかね困惑しているのか、曖昧に微笑み、タクシーを呼ぶよ、と店に戻ろうとした青年の手首を、男は咄嗟に掴んだ。
「これからファルコンで飲み直す。…お前も来るか?」
レストランの入口の黄色い照明の下、ひどく驚いた顔をしたルークは、しばし逡巡した後、頷いた。